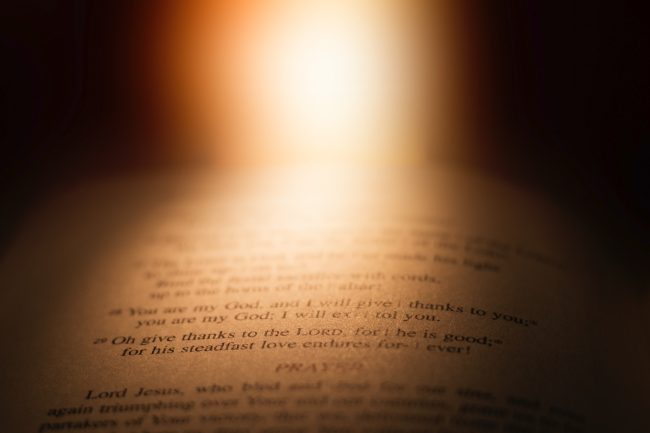不信仰
出エジプト記4章1~17節(旧98頁) ヨハネによる福音書20章24~29節(新210頁) 前置き 前回の出エジプト記の説教では、神の御名について話しました。神には、色々な名前がありますが、その中で聖書に一番最初に出てくる名前は「私はある。」(ヘブライ語でエへイェ·アシェル·エへイェ、ギリシャ語でエゴ·エイミ)でした。これを意訳すると「私は自ら存在する者」という意味になりました。神はご自分の名前を「自ら存在する者」と言われました。自ら存在する神は、すべてのものの根源、創造主である方です。この世のすべては、神によって造られ、神以前の存在はありません。エジプトからの脱出を命じられた神は、モーセを遣わされる前に、すでにご自身が「万物を超越する者、最初から存在する者、自ら存在する者、絶対者」であることを示されたのです。ですから、出エジプトは絶対に成功します。被造物であるエジプトが創造主である「自ら存在する神」に勝つことはできないからです。私たちは、この「わたしはある」という御名の神を信じています。この世での苦しみと悲しみの中で、私たちが希望を持って生きる理由は、私たちが崇める神が、この世を支配する「自ら存在する者」であるためです。そして、自ら存在する神であり、完全な人間として来られたイエス·キリストが私たちの頭でおられるからです。 1.主の御言葉と自分の考えとの間で。 神はモーセに「エジプトに行って、わが民イスラエルを連れ出してきなさい。」と命じられました。ミディアンで40年以上、一介の羊飼いとして生きてきたモーセに、ある日突然現れた神は、モーセにとっては到底無理な務めを任せられたわけです。イスラエル人に生まれたが、エジプト王女の養子として育ち、一時は権力と野望を持っていたモーセ、しかし、若い頃の彼の野望(政治的にイスラエルを解放すること)は、あまりにも簡単に失敗してしまいました。すでに一度失敗した彼に突然現れた「先祖たちの神」は、年老いた羊飼いにあり得ない、無理な要求をしているようでした。モーセは、経験的に「イスラエル解放」が、どれほど難しいことかをよく知っていたからです。そのため、モーセは何度も逆らいます。「わたしは何者でしょう。どうして、ファラオのもとに行き、しかもイスラエルの人々をエジプトから導き出さねばならないのですか」(出3:11)「ああ、主よ。わたしはもともと弁が立つ方ではありません」(出4:10)「ああ主よ。どうぞ、だれかほかの人を見つけてお遣わしください。」(出4:13) 神が「あなたが行って、わたしの命令を行いなさい。」と命じられたのに、なぜ、モーセは「私には出来ません」と言うのでしょうか? それは神へのモーセの不信仰に基づきます。もちろん、モーセの立場が理解できないわけではありません。誰でも初めて出会った人の言うことを簡単に従うことはできないと思います。しかし、神は明らかに言われました。「わたしはあなたの父の神である。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。」(出3:6) 今日の本文でモーセが出会った神は「初めて会う方」ですが、「全く知らない存在」ではありませんでした。自分の先祖の先祖、一時、エジプトの総理として偉業を成し遂げた、あの「ヨセフ」の父親と祖父と曾祖父の神です。王女の養子になる前に、実母のもとで育てられたモーセは、おそらく、神と先祖たちについての話を数え切れないほど聞いたことでしょう。また、その方がいつか来られ、乳と蜜の流れるカナンにイスラエル民族を導いていかれるという話も繰り返し聞いたに違いありません。ところで、その「先祖の神」という存在が、ある日突然モーセ本人の前に現れられたというわけです。神という超越的な存在が「いつかは」現れて、同胞イスラエルを救い出してくださると漠然と信じていたかもしれませんが、その方がまさに今日、自分自身の前に現れ、イスラエルの解放を命令された時、モーセはどれほど驚いたでしょうか? 果たしてモーセは、その命令に従うことができたでしょうか? 私たちにそういうことがあったら、私たちはどう対応したでしょうか。 そんな突然の状況のため、モーセは先祖との契約という神の御言葉と自分の経験の間で迷っており、それがモーセの不信仰につながったわけです。経験はとても大切なものです。「白髪(年寄りの知恵)は輝く冠、神に従う道に見いだされる」(箴言16:31)ということわざのように聖書は経験による知恵を大切に取り扱っています。しかし、その経験が神の御言葉と約束を妨げる障害物になってしまうと、むしろ、その経験は不信仰の種になる可能性もあります。自分の経験と考えは大事ではありますが、あまり信用しないように気をつける必要があります。自分の判断に陥って何もできない者になってはなりません。私たちの価値基準は、唯一神の御言葉によってのみ決まるべきものです。不可能に見えても、神がおっしゃるなら信頼するのです。今日のモーセは自分の経験、価値基準、思いにとらわれ、神の命令に聴き従うことが出来ませんでした。そして、こんな姿が、今日の私たちにも、同じくあり得るということを忘れないようにしましょう。今日、突然主が現れて私たちに主の計画の実行を命じられたら、私たちは主の御言葉と私たちの経験の間で、どのように行動するようになるしょうか? 信仰を持つ者には、こういう課題がいつも伴います。 2.主が見せてくださったしるしの意味。 モーセが逆らうと、神は二つのしるしを見せてくださいます。それらは「モーセの杖を蛇に変えられること」と「モーセの手に重い皮膚病をかからせ、治してくださること」でした。この二つのしるしはもちろん現実では起こり得ない非常に不思議なことでした。しかし、このような魔術みないなことを果たして偉大な神のしるしだと言えるでしょうか? しかし、私たちはこの二つのしるしから、神の御業の象徴性について学ぶことができます。まず、杖が蛇になって、また杖になるしるしには、どういう意味があるでしょうか? モーセの杖は羊飼いの道具です。ですから、遊牧民族だったアブラハムやイサクやヤコブの子孫イスラエルは、杖という道具に親しみを持っていたでしょう。また羊飼いのモーセ個人にとっても、杖は毎日使っていた、とてもなじみのある道具でもあったのです。そして、蛇はエジプトの王権を象徴する動物だと言われます。時々、エジプト関連の番組や絵で、ファラオの帽子のコブラ(蛇)の形の飾りをご覧になったことがあると思います。神は杖に象徴される、すでに力もなく野望もない平凡なヘブライ人モーセを用いられ、蛇に象徴されるエジプト・ファラオの尾をつかんで、何の抵抗もできないように制圧されるでしょう。元々、蛇の尾は絶対につかんではならないと言われます。蛇が首を回して噛むからです。しかし、モーセが蛇の尾をつかんだとき、蛇はモーセの日常の道具である杖に戻りました。結局、エジプトのファラオは、神と一緒に歩むモーセに、何の害も及ぼすことができず、屈服することになるでしょう。 次に、モーセの手に重い皮膚病がかかって治ったことです。これも不思議な出来事ですが、何か感動的で畏敬の念を憶えるほどのしるしではないと思います。日本には同様のことわざがあるかどうか分かりませんが、韓国には「病気を与え、薬も与える。」ということわざがあります。他人を困らせたり、いじめたりした後、善意を施し助けるふりをする、偽善的な人間を批判する表現です。神はこの「病気を与え、薬も与える。」ためにモーセの手に皮膚病と回復をくださったでしょうか。もちろん、そうではありません。神が皮膚病のしるしを見せてくださったことには、確かな理由があります。本文の皮膚病とは、ハンセン病だと思われます。皮膚の感覚が鈍くなっていき、後には指や足指、鼻などが落ちてしまう、非常に深刻な皮膚病なのです。今では、医学の発達により、ハンセン病者が少ないですが、昔には社会から隔離されたり、殺害されたりするほど、恐ろしい病気だったのです。そのため、昔の人々はハンセン病にかかることは、まるで死ぬことであるという認識を持っていました。つまり、神がモーセの手をハンセン病にかからせ、治されたということは、神こそが「生と死」を司る絶対者であることを象徴的に表すことだったのです。だから、二つのしるしは、単純な魔術のような出来事ではなく、絶対者である神の偉大さを示す、はっきりとしたメッセージだったのです。 3.一人ではなく、一緒に信仰にあって進もう。 「それでもなお、モーセは主に言った。ああ、主よ。わたしはもともと弁が立つ方ではありません。あなたが僕にお言葉をかけてくださった今でもやはりそうです。全くわたしは口が重く、舌の重い者なのです。」(出4:10)神が、このような二つのしるしを見せてくださったにもかかわらず、モーセは自分にはできないと相変わらず不信仰の態度を見せます。自分は口が重く、舌が重い者であるということです。神は最後まで逆らうモーセに「一体、誰が人間に口を与えたのか。一体、誰が口を利けないようにし、耳を聞こえないようにし、目を見えるようにし、また見えなくするのか。主なるわたしではないか。さあ、行くがよい。このわたしがあなたの口と共にあって、あなたが語るべきことを教えよう。」(出4:11-12)と明確に言われます。それと共に「あなたにはレビ人アロンという兄弟がいるではないか。わたしは彼が雄弁なことを知っている。その彼が今、あなたに会おうとして、こちらに向かっている。」(出4:14) とも言われました。モーセの兄アロンが、モーセを手伝い、また、二人と共に主がおられ、助けてくださることを言われました。不信仰は望ましいものではありませんが、誰でも、自分の経験や勇気不足によって不信仰の姿になりえます。私たちは皆、モーセのように弱い存在だからです。しかし、主は一緒に信仰を守りつつ、前に進んでいく協力者を与えてくださり、また、主ご自身も一緒に歩んでくださいます。なぜ、絶対者であるキリストが、不完全な私たちを召され赦し、一つにしてご自分の体である教会と呼んでくださったでしょうか。弱い者たちを一つにされ、共に歩んでくださるためではないでしょうか。 締め括り 今日の説教のタイトルは不信仰でしたが、信仰の弱さを責めようとして、説教を書いたわけではありません。誰もが、このモーセのように、神の突然のご命令の前で、迷ってしまうでしょう。だからこそ、人間なのです。しかし、私たちにおいての、突然の神のご命令が、神においては、天地創造の前に、すでに計画されていたものであることを忘れてはならないと思います。だから、私たちが、まだ準備できていない時でも、神はすでに準備を終えられ、私たちにご命令なさるのです。自分としては理解できなくても、神のご計画とお導きを信頼して黙々と聞き従っていくこそが信仰なのです。日常生活で、到底理解できない神の導きを感じる時がたまにはあります。やりたくない命令がある時もあります。そんな時は、自分の経験と考えをしばらく止めて、主イエスはこんな時どうなさるだろうかと考えてみましょう。神のご命令にすべての判断を止められ、十字架にかかられ、ご自分の民を救ってくださったイエス·キリストの御心を憶えてください。おそらく、イエスは今日の新約本文でトマスにおっしゃったように「信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」と勧められるではないでしょうか? 神の御言葉に迷う時があっても、完全に信じられない人にはならないようにしましょう。不信仰を乗り越えて信仰の道に進んでいく志免教会の兄弟姉妹でありますように祈ります。 父と子と聖霊の御名によって。 アーメン。