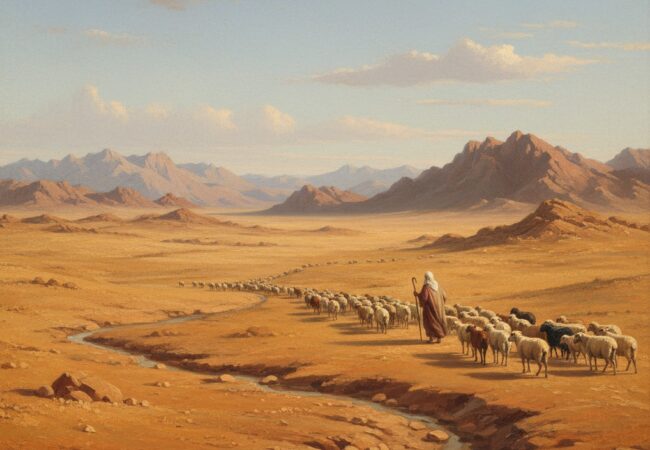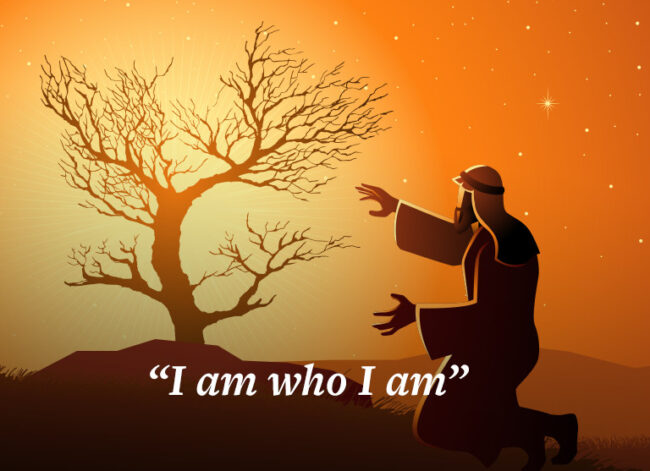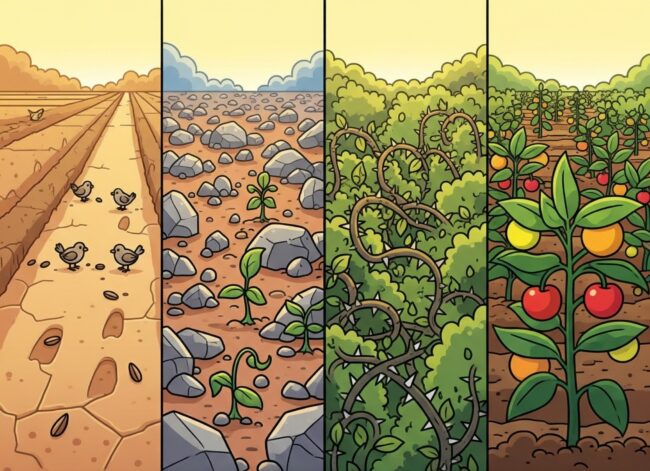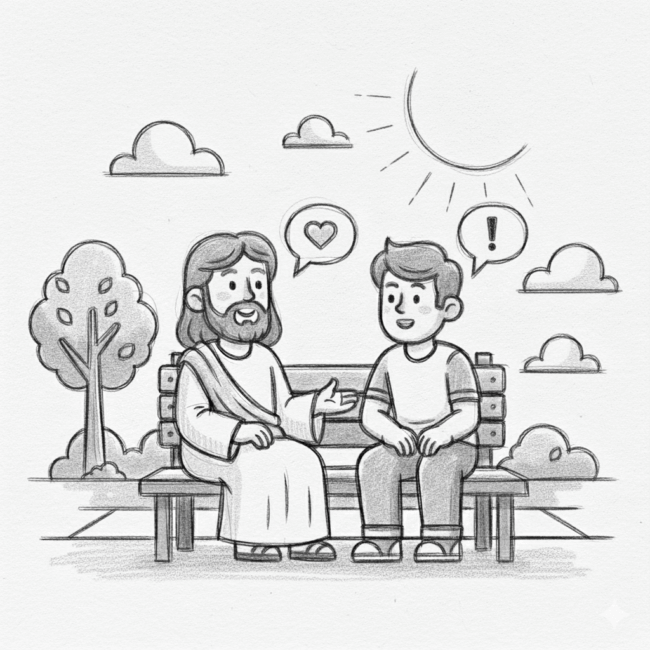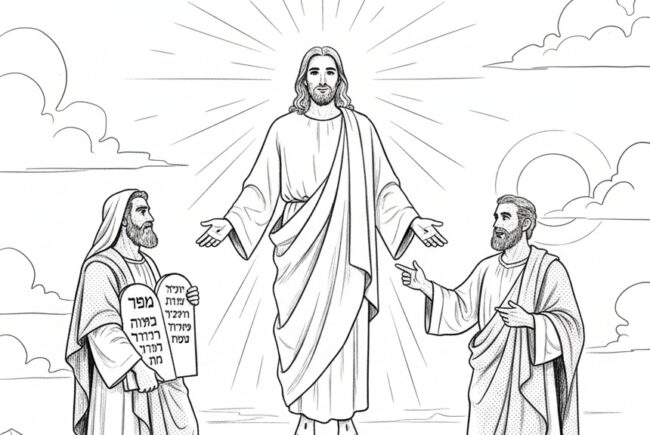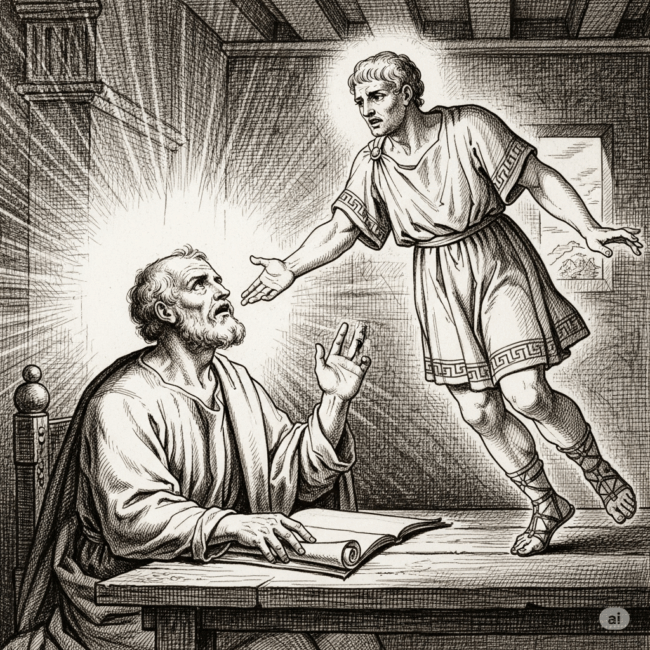私たちのいるべき場所
出エジプト記 2章11~25節(旧95頁) ローマの信徒への手紙14章8~9節(新294頁) 前置き イスラエルの先祖であるヤコブとその一族は、主なる神の御導きにより、ひどい飢饉を避けてエジプトに移住しました。ヤコブの子孫はエジプトで栄え続け、数十万人の民族に成長しました。しかし、ヤコブの時代の友好的なエジプトの王朝が滅び、他の王朝が復権して、ヤコブの子孫イスラエルに大きな試練が迫ってきました。しかし、それはイスラエルを滅ぼすための試練ではなく、それによって目を覚まし、主と先祖の約束の地、イスラエル民族のいるべき場所であるカナンに導かれる主なる神のご計画でした。主の民にはいるべき場所があります。いくら満足し、安らかなところにいるといっても、主のみ旨に適わない場所なら、そこはキリスト者のいるべき場所ではありません。主の民のいるべき場所ではなく、主と関係のない自分の罪の本性が願う場所にいる時、主は試練と苦難を装った御導きによって、ご自分の民の目を覚まさせ、主が備えてくださる場所に立ち戻る準備をさせてくださいます。出エジプト記は「主の民のいるべき場所」についての物語なのです。 1. 主の御業は人間の手によっては成し遂げられない エジプト王のイスラエル民族への弾圧を避け、ナイル川に捨てられた赤ちゃんモーセはファラオの王女に拾われ、エジプトの王宮に入りました。幸いにも、モーセは主の恵みによって実母を乳母に育つことが出来、「ヘブライ人」のアイデンティティを失わずにエジプト人として成人するようになりました。王女の息子モーセは当時の高級学問を学んでエリートとなり、エジプト社会で無視できない存在となりました。モーセはヘブライ人とエジプト人の境界にいる存在でした。おそらく、そんな位置だったモーセは、自分がヘブライ人を政治的に救う人物だと思い込んでいたかもしれません。彼だけがエジプトでの権力とヘブライ人への理解が両立する人だったからです。「モーセが成人したころのこと、彼は同胞のところへ出て行き、彼らが重労働に服しているのを見た。そして一人のエジプト人が、同胞であるヘブライ人の一人を打っているのを見た。モーセは辺りを見回し、だれもいないのを確かめると、そのエジプト人を打ち殺して死体を砂に埋めた。」(出2:11-12) しかし、そんなモーセの情熱が問題となってしまいました。ヘブライ人を助けるために、エジプト人を殺してしまったからです。彼はエジプト人の遺体を沙に隠し、なかったことにしようとしました。 「翌日、また出て行くと、今度はヘブライ人どうしが二人でけんかをしていた。モーセが、どうして自分の仲間を殴るのかと悪い方をたしなめると、誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、このわたしを殺すつもりかと言い返したので、モーセは恐れ、さてはあの事が知れたのかと思った」(出2:13-14)モーセが再びヘブライ人のところに行き、争いを仲裁しようとした時、一人がモーセに言い返しました。「誰がお前を我々の監督や裁判官にしたのか。お前はあのエジプト人を殺したように、このわたしを殺すつもりか」誰も知らないと思っていたのに、多くの人がモーセの殺害を知っていたわけです。ヘブライ人ではあるが、後ろ盾の王女によって、エジプト社会の一員となったモーセ。しかし、エジプト人殺害によって彼に敵対していたエジプトの何人かの権力者たちは、彼を攻めようとしたでしょう。だけでなく、ヘブライ人も彼を認めませんでした。そこでモーセは持ちこたえられず、エジプトから逃げてしまいました。モーセは自分の背景と権力を用いてヘブライ人の指導者になり、イスラエルを解放させようとしていたのかもしれません。彼には力と知識があったからです。しかし、彼の自信は、むしろ自分の計画を潰す障害となってしまいました。意気揚々だった彼は、一晩にエジプト人にも、ヘブライ人にも、認められない逃亡者になってしまったのです。 以上を通じて、私たちは主なる神の御業の成就について学ぶことが出来ます。主の御業は人間の情熱や力によって成し遂げられるものではありません。私の大学生の頃、韓国の教会では「高地論」という言葉が流行しました。文字通りに「キリスト者が社会の高い位置を占め、社会を変革する」という思想でした。ところが、二十数年たった今、韓国の教会はその社会でそんなに評判ではありません。一部のことですが、元大統領の不正にかかわった疑惑もあります。恥ずかしい現実です。また、日本の教会にも、高地論のような思想があるかもしれません。数年前、金子道仁という牧師が参議院議員に当選しました。他教派ではかなり人気だったと覚えています。彼を支持するキリスト者の中には、彼が高い位置に上がって日本社会に大きい影響を及ぼすだろうと、日本の教会の希望であるかのようなニュアンスで支持する人もいました。私個人も金子さんがとても立派な方だとは思いますが、彼によって日本社会が変革したとは言えません。世界を変えるというのは、特別な一人に託されるものではありません。唯一主なる神だけがご自分の御手を通して、御心によって成し遂げられる事柄です。教会は、そのために主の手と足として用いられるだけで十分です。もし教会が神の御心と関係なく自分で世を変えようとしたら、今日の本文のモーセのように困難な目にあってしまうかもしれません。 2. 主の御業は御心に基づいてのみ成し遂げられる。 だからといって「教会は何もしなくて良いから」という意味ではありません。先の金子道仁さんのような政治家は参議院議員という自分の場所で、また、志免教会のみんなは、めいめい日常の場所で、主に命じられた神と隣人への愛、そして福音伝道に努めていけば良いと思います。そのような日常の中で、主はご自分の御心に基づき、教会を用いられて世界を変えていかれるでしょう。私たちに出来るのは、主の御言葉に聞き従いつつ、日常を生きることだからです。「ファラオはこの事を聞き、モーセを殺そうと尋ね求めたが、モーセはファラオの手を逃れてミディアン地方にたどりつき、とある井戸の傍らに腰を下ろした。」(出2:23-25) エジプトから脱出したモーセは、ファラオの脅威を避け、ミディアン地方へ逃走しました。ミディアンは現在のアラビア半島の北西部を意味しますが、牧畜をしながら、流浪する、アブラハム系の一族の名でもありました。ミディアン地域は砂漠であるため、羊の餌が足りず、頻繁に移動しなければなりません。つまり、モーセは大帝国での落ち着いた生活から離れ、決まった場所なく、移動し続けなければならない不安定なミディアンでの生活へと、その居場所が変わったのでした。 「モーセがこの人のもとにとどまる決意をしたので、彼は自分の娘ツィポラをモーセと結婚させた。彼女は男の子を産み、モーセは彼をゲルショムと名付けた。彼がわたしは異国にいる寄留者(ゲール)だと言ったからである。」(出2:21-22)ミディアンの祭司の配慮で落ち着くようになったモーセは、以後「ツィポラ」という名の妻をめとり、息子「ゲルショム」をもうけました。そうして、モーセはエジプトのエリートからミディアンの平凡な羊飼いへと、その位置が変わったのです。もはやモーセには昔の権力も地位もありませんでした。しかし、皮肉なことに彼がこんなに普通の人になった時、主なる神は彼に現れ、イスラエルの指導者に立ててくださいます。先ほど前置きでお話ししましたように、キリスト者には自分のいるべき場所があります。モーセはエジプトの王子のように育ちましたが、そこは彼の居場所ではありませんでした。モーセは自分の権力と知識でヘブライ人を導こうとしましたが、そこも彼の居場所ではなかったのです。彼の居場所は剣を持った政治的な指導者ではなく、杖を持ったごく平凡な羊飼い、このミディアンでの生活でした。しかし、彼がそうなった時はじめて、主なる神は彼を訪れて来られたのです。 「それから長い年月がたち、エジプト王は死んだ。その間イスラエルの人々は労働のゆえにうめき、叫んだ。労働のゆえに助けを求める彼らの叫び声は神に届いた。神はその嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの人々を顧み、御心に留められた。」(出2:23-25) そして、昔モーセがやろうとしたイスラエルの指導者の業を、主は改めて彼にお委ねになりました。40歳ごろ、モーセが情熱と血気で目指したイスラエルの解放は、実は神の御業ではありませんでした。それはモーセ自身の業だったのです。しかし、モーセがミディアンの羊飼いとなり、何の力もなくなった時、主なる神はイスラエルの先祖たちとの契約を思い起こされ、80歳の羊飼いモーセを召され、主の御業に招いてくださったのです。つまり、主の御業は主の時に、主のご意志によって成し遂げられるということです。また、主の御業は、人の意志や情熱ではなく、ご計画と約束によって、私たちに与えられるものです。重要なのは「私たち自身の情熱」ではなく「主なる神の御心」ということです。教会のあり方は徹底して主の御心に自分の歩みを合わせることです。そして、その主なる神がご自分の手を差し伸べられる時、教会は喜んで御手の道具として用いられるべきです。 締め括り 「わたしたちは、生きるとすれば主のために生き、死ぬとすれば主のために死ぬのです。従って、生きるにしても、死ぬにしても、わたしたちは主のものです。」(ローマ書14:8) 前置きで「キリスト者には自分のいるべき場所がある」と申し上げました。モーセは王宮での王子のような生活ではなく、荒野の羊飼いのような生活の中で、主なる神に出会い、真のイスラエルの指導者と召されました。人の目にはみすぼらしいミディアンの荒野が、主の御目にはイスラエルの指導者がいるべき最適な場所だったのです。私たちも時には、今こそ我が教会が動く時、あるいは何とかやらなければならないと気を揉む時があるかもしれません。しかし、そのたびに私たちは思い起こさなければなりません。今現在、自分がいるべき場所はどこか。自分のやるべきことは何か。「自分のために生きるのではなく、主のために生き、死ぬ人生」を憶え、私たちのいるべき場所を憶える一週間を過ごしてまいりましょう。