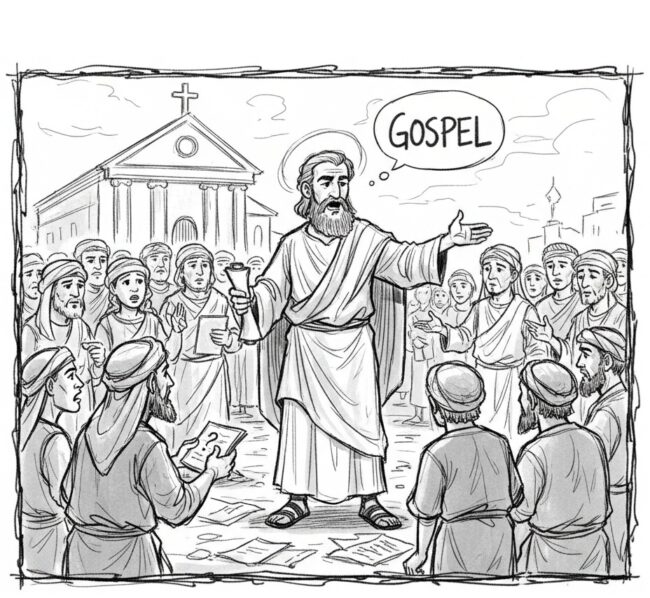アドベントの意味
イザヤ書65章17-25節(旧1168頁) ペトロの手紙二3章8-13節(新439頁) 前置き アドベント即ち待降節の時になると、多くの教会がクリスマス飾り、4本のロウソクなどを用意し、主イエスのご降誕を祝います。また、クリスマスまでの約1ヶ月間、天の玉座から低い地上の飼い葉桶までおいでになった赤ん坊イエスを待ち望みつつ、聖書の黙想と祈り、教派によっては断食などを通して、 イエスのご誕生を記念します。それゆえに、多くの人々がこの待降節を主イエスのご誕生だけのための準備期間として理解しがちだと思います。しかし、待降節が持つ大事な意味は、単に受肉してお生まれになった初臨のイエスだけでなく、いつか再び臨まれる再臨の主イエスをも共に記念することにあります。したがって、待降節は主イエスのご誕生とともに、再臨される主イエスを記念する期間でもあります。昔、主イエスはなぜこの地上にお生まれになり、将来、主イエスはなぜこの地上にまたおいでになられるのでしょうか。今日はアドベントの意味を通して、おいでになったイエスと、おいでになるイエスについて話してみましょう。 1.待降節の起源と意味 現代は、太陽暦を使用して1年を数えています。しかし、古代と中世の教会はキリストの生涯、特にクリスマスとイースターを中心とした教会暦によって1年を数えたと言われます。教会暦によると、待降節が始まる主日が1年の初日だったそうです。つまり教会暦は主イエスのご誕生を期して1年間を始めたということです。日本の教会では待降節をアドベントと呼んでいます。待降節、つまり「主のご到来を待つ期間」という良い漢字語の表現があるのに、なぜ人々は、あえて外来語を使用しているのでしょうか。「アドベント」は「到来」を意味するラテンAdventus(アドベントス)に由来します。主イエスのご到来を記念しようという意味で、外来語をそのまま借用したので、今でもアドベントという表現を使っているのです。というわけで、アドベントの意味を知らずに、漠然と使っている人が多いでしょう。しかし、大丈夫です。アドベントは外来語ですが、その意味だけは待降節とまったく変わりがないからです。大事なのは、救いと平和の主イエス・キリストが、この地上にご到来なさったこと、それを憶えるにあるのではないでしょうか。 もともと待降節は、キリストの神性が、公に現れたことを記念する公現祭の準備期間だったと言われます。公現祭とは、貧しい大工の息子として、お生まれになった赤ん坊イエスのところに、東方からの占星術学者たちが訪れ、主イエスの出生が、実はいと高き神の子の顕現であることを、この世に公に現したことを記念する日なのです。待降節は、この公現祭を記念する期間だったのです。そのような待降節が時の経つにつれてクリスマスを記念する日と変わったわけです。教会は、最初はキリストのご誕生だけを記念して待降節を過ごしましたが、西暦6-7世紀頃に再臨のイエスへの待ち望みの意味も付け加えて、今の待降節はイエスの初臨と再臨を共に記念する意味を持つようになったと言われます。とにかく、待降節はイエスのご到来を記念する重要な期間です。日本ではクリスマスがハロウィンのように外国からの祭りとして、軽く取り扱われているようです。しかし、主の教会は、待降節の期間を通して、御救いのために初めて臨まれた主、また御裁きのために再び臨まれる主を憶えつつ慎んで過ごすべきでしょう。かつて、この地上に来られ、罪によって苦しんでいる人間を愛し、赦してくださった主の御救いと平和を憶え、また、やがて、再び来られる主の公平な御裁きを待ち望みつつ、この期間を過ごしましょう。 2.キリストの初臨 – 約束のメシアがおいでになる。 キリストのご誕生が大事な理由は、旧約のメシア信仰の成就という大きな意味を持っているからです。旧約のイスラエルには、神のメシアが、いつか到来し、この世を裁き、主の民を救ってくださるという信仰がありました。彼らは、メシアが来て、人間では成就できない真の癒しと慰めを与えくださると信じたのです。貧しい者、病んでいる者、縛られている者、閉じ込められている者、絶望に陥った者に、力を与え、導いてくださる存在が、まさにこのメシアだと信じていたわけでした。「主はわたしに油を注ぎ、主なる神の霊がわたしをとらえた。わたしを遣わして、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために。打ち砕かれた心を包み、捕らわれ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために。」(イサヤ61:1)このようにメシア信仰は、主なる神がこの世で苦しんでいる民を見捨てられず、いつか必ず救ってくださるという、神への信頼と希望、この世の悪への抵抗という意味を持っていました。 教会が主イエスのご誕生を大切にする理由は、この旧約のメシア信仰がイエス・キリストによって成就されたと信じているからです。 イエスは永遠な神ご自身が、人間になって来られた存在です。元々神は人間と全く別の存在で、神学的には絶対他者と呼ばれる方です。創り主なる神が、被造物である人間になるのは有り得ないことであり、神と人間の間には絶対に共有できない神性と人性という雲泥の差があります。しかし、神は人間を赦し、救われるために神性とともに、人性を持って自ら人間になってくださいました。これはご自分の創造の秩序を自らくつがえされた神の特別な恵みです。このような例えはいかがでしょうか。(神の受肉とは比較できませんが、あえて例えれば) 人間が虫になるのは有り得ないことです。もし誰かが虫を助けるために、自ら虫のような存在になれば、それは映画に出てきそうなことでしょう。ところが、神は罪によって堕落した虫のような人間の救いために、自ら人間になって来られたのです。さながら映画のような出来事がイエス•キリストのご誕生によって、この地に起こったわけです。自ら人間になって来られた神であるイエスは、ご自分の命を捨ててまで、人間に代わって死に、復活して罪を赦してくださいました。そして、この世の終わりの日まで、ご自分を信じる者たちのために執り成してくださるでしょう。真のメシア主イエス•キリストは人間を愛し、被造の世界を神に導いてくださる、たったお独りの方です。 キリストのご誕生は、そのメシアであるイエスの最初の歩みなのです。 3.キリストの再臨 – 最も完全かつ新しい創造 それでは、待降節はなぜ、このようなイエスのご誕生だけでなく、イエスの再臨をも記念するのでしょうか。今日の旧約の本文を読んでみましょう。「見よ、わたしは新しい天と新しい地を創造する。初めからのことを思い起こす者はない。それはだれの心にも上ることはない。代々とこしえに喜び楽しみ、喜び躍れ。わたしは創造する。見よ、わたしはエルサレムを喜び躍るものとして、その民を喜び楽しむものとして、創造する。わたしはエルサレムを喜びとし、わたしの民を楽しみとする。泣く声、叫ぶ声は、再びその中に響くことがない。」(イサヤ65:17-19)私たちは、神が永遠な方であることを聖書を通じて学び、すでに知っています。ここで永遠とは何でしょうか。哲学では「永遠」と「不滅」という概念があります。私たちは、よく永遠を不滅と混同したりします。 永遠は「限りなく長く存在する。」という「不滅」とは異なる概念です。永遠とは、「最初から最後まですべてが完全に支配される。」という意味を持っています。 私たちは創世記を通じて、神がこの世をお造りになったことを学びました。ところで、聖書は、その神が終わりの日に、この世を再び新たに創造されることをも示しています。つまり、昔の創造と新しい創造の間のすべてを、神が司っておられるのです。その中には空間、時間の全ても含まれているのです。それがまさに聖書が語る永遠の本当の意味なのです。 主イエスの再臨とは、この新しい創造が完成する日のことです。神の初ての創造は、人間の罪によって汚されてしまいました。神は人間を被造物の頭としてくださいました。ところが、その頭である人間という存在が堕落し、神の被造の世界も堕落してしまったのです。イエス•キリストは初臨して、ご自分の犠牲を通して人間と被造の世界を救う手立てを備えてくださいました。そして、その象徴として主の教会を建ててくださったのです。教会の頭なるイエスは再び来られて、必ず救いを成し遂げてくださるでしょう。その時、主に逆らう邪悪な者は裁かれ、主に従う正しい者は救われるでしょう。「神の日の来るのを待ち望み、また、それが来るのを早めるようにすべきです。その日、天は焼け崩れ、自然界の諸要素は燃え尽き、熔け去ることでしょう。しかしわたしたちは、義の宿る新しい天と新しい地とを、神の約束に従って待ち望んでいるのです。」(ペトロ二3:12-13)すなわち、御裁きと御救いは、キリストによる新しい創造の一面に過ぎないものです。再び来られる主は、神がご計画なさった最も完全な創造を成し遂げられるでしょう。そして、その新しく創造された世で、主の民である私たちは、至高の喜びと愛とを持って主と永遠の中に、一緒に生きるでしょう。私たちが待降節を通して、主の再臨を待ち望む理由は、主の再臨に新しい創造という意味が隠れているからです。 締め括り 待降節を通して、初臨と再臨のイエス•キリストを憶える時を過ごしましょう。この世での私たちの人生がいつも幸せだとは限りません。人にはいつか必ず死ぬことが定まっており、喜びより悲しみが多いのが、この世の有様です。しかし、主イエスは、悲しみと死を圧倒する真の喜びと生命が、ご自分の中にあると教えてくださるために、いと高き天から低い地上に来られました。そして、いつか父なる神の右から、ご自分の中にある真の喜びと生命を完全に成し遂げてくださるために、まさに新しい創造のために必ず再び来られるでしょう。このような、かつて臨まれたイエスと、また、いつか臨まれるイエスを記念し、待降節とクリスマスを過ごしたいと思います。愛と救い、平和と新しい創造の主イエス•キリストが、私たちと共におられ、限りのない祝福を与えてくださることを祈り願います。