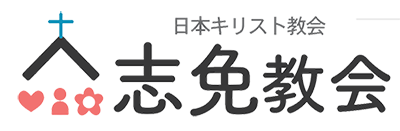安息日論争
申命記5章12-15節(旧289頁)マルコによる福音書2章23-28節(新64頁) 前置き 前回のマルコ福音書の説教では断食について話しました。断食とは、自ら飲食を断ち、肉体の欲望を抑え、罪を悔い改め、自分のことを省みるための行為でした。旧約では年に一度、贖罪日に断食を行うことで自らを反省し悔い改めたようです。(レビ記23:27)また、時間が経ち、断食は貧しい隣人を助けるという意味も持つようになりました。(イザヤ58:6)しかし、このように断食が持つ立派な精神は、イエスの時代に至っては偽善的な宗教儀式に変質してしまったようです。(マ6:16)イエスはそうした偽善としての断食を強く拒否されました。 私たちは、前回の説教で、この断食という代表的な宗教儀式を例に挙げ、偽善的な宗教行為に陥らず、神への信仰と隣人への愛とを持って生きるべきだと学びました。こんにちの私たちには宗教儀式としての断食を行う機会はあまりありません。しかし、私たちは依然として、礼拝、献金、祈りなど、宗教儀式の中で生きています。 イエス様が偽善的な宗教行為としての断食を拒否されたように、私たちも、また信仰生活が偽善的な宗教儀式にならないように注意しなければなりません。私たちは、ひたすら神と隣人への愛を示す手立てとして、宗教儀式を追い求めて生きるべきでしょう。 1.安息日についての論争が起こった理由。 「ある安息日に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは歩きながら麦の穂を摘み始めた。 ファリサイ派の人々がイエスに、御覧なさい。なぜ、彼らは安息日にしてはならないことをするのかと言った。 」(23-24)ある安息日に、イエスと弟子たちが麦畑を通っていました。 彼らは道をつけるために(直訳ギリシャ語)、穂を摘みました。それを見たファリサイ派の人々が抗議しました。「どうして安息日にしてはならないことをするのか。」彼らはなぜ抗議したのでしょうか。もしかして、イエスと弟子たちが麦畑を荒らすことを糾弾するつもりだったのでしょうか? これと同様の本文がマタイによる福音書にも出て来ていますが、「ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。」(マ12:1)と表現されています。 旧約聖書の申命記23:25には、これに関する規定があります。「隣人の麦畑に入るときは、手で穂を摘んでもよいが、その麦畑で鎌を使ってはならない。」つまり、イエスと弟子たちが道を作りながら麦の穂を摘んで食べたのは、犯罪行為ではなく、社会的に許された合法的なやり方でした。ところが、ファリサイ派の人々は彼らの行為を見て、「安息日にしてはならないこと」だと叱ったのです。弟子たちの行為は不法じゃなかったのに、なぜファリサイ派の人々は彼らを非難したのでしょうか? その理由は、イエスと弟子たちが昔の人の言い伝えを破っていると考えたからです。この昔の人の言い伝えとは、モーゼ五書を解説した『ミシュナー』という解説書を意味するのですが、有名なラビたちが残した記録でした。このミシュナーにはモーゼ五書ほどの権威は無く、その中にはラビたちの個人的な主張も含まれていて、神の御言葉だとは言えない書でした。しかし、ユダヤ人は、それを聖書に次ぐものと重要に扱い、それを中心に数多くの規定を作り出しました。その中には安息日に関する解説もありましたが、例えば「安息日に働いてはならない。だから、旅をして800M以上歩くことを禁止。人が壁の下敷きになっても石の退かすことを禁止。隣の牛が穴に落ちても救うことを禁止。」などのように、とんでもないことが安息日の禁止規定となっていたそうです。宗教的に重要な安息日を守るためには、他人への奉仕や愛の行為はやめるしかないと思ったわけです。もともと旧約に記された安息日の労働禁止は、自分の欲望、娯楽のために働いてはならないという意味だったのに、昔の人たちは、それを極端に誤解したわけでした。それで、ファリサイ派の人々は弟子たちが安息日に麦畑の穂を摘んだことを労働だと見なし、昔の人の言い伝えを破っていると主張したわけです。 2.神が安息日を制定された理由 イエスのお働きを補助していた弟子たちは、おそらく食事を済ます時間さえなかったでしょう。そんな彼らが、お腹を満たすために麦畑の穂を摘んだことは、もしかしたら生きるための最小限の行為だったのかもしれません。しかし、ファリサイ派の人々は彼らの事情には関心がありませんでした。 彼らは昔の人たちが残した歪んだ言い伝えを用いて、イエスと弟子たちを責めることにだけ関心があったのです。神は、なぜイスラエルに「安息日を守ってこれを聖別せよ。」という律法を与えられたのでしょうか? 安息日を宗教的な日と定め、人間を束縛し、神様に礼拝だけさせるために造られたのでしょうか? 旧約本文の申命記の十戒はこのように語っています。「あなたはかつてエジプトの国で奴隷であったが、あなたの神、主が力ある御手と御腕を伸ばしてあなたを導き出されたことを思い起こさねばならない。そのために、あなたの神、主は安息日を守るよう命じられたのである。」(申命記5:15)神は、かつてエジプトの奴隷として生きていたイスラエルに、真の自由をくださるために安息日を制定されました。神は強い者が弱い者を弾圧し、自分の欲望を満たしていたエジプトの間違った文化を打ち破り、弱い者をも人間らしく生きさせられるために安息日をくださったのです。 つまり、神がイスラエルを尊く思われ、安息日をくださったという意味です。古代社会において弱い者には人権がありませんでした。彼らは家畜や品物のような存在でした。強い者が命じると死ぬしかなく、差別は当然のことでした。古代中東社会で安息というのは神々、王族、祭司だけの特権であり、弱い者たちは彼らの特権のために死ぬほど仕えなければならない存在に過ぎなかったのです。そのような社会で神は弱い者たちにも安息という特権をくださるために安息日を造られたわけです。 弱い者を王のように扱ってくださったという意味です。 「七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも、息子も、娘も、男女の奴隷も、牛、ろばなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に寄留する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷もあなたと同じように休むことができる。」(申命記5:14)それは、単にイスラエルにだけ適用されることではなく、家畜、異民族、よそ者にも同じことでした。このように安息日は神の支配の下にある、すべての存在に許された自由と平和の日でした。それなのに、ファリサイ派の人々は、人よりも宗教儀式に目がくらみ、人を憐れまず、罪に定めるだけでした。 3.安息日は人のためにある。 「イエスは言われた。ダビデが、自分も供の者たちも、食べ物がなくて空腹だったときに何をしたか、一度も読んだことがないのか。 アビアタルが大祭司であったとき、ダビデは神の家に入り、祭司のほかにはだれも食べてはならない供えのパンを食べ、一緒にいた者たちにも与えたではないか。」(2:25-26)イエスは安息日に弟子たちが麦の穂を摘んだことを咎めるファリサイ派の人々に、イスラエルの代表的な王、ダビデを挙げて仰いました。サムエル記Ⅰ21章で、ダビデが自分を殺そうとしていたサウル王を避けて逃げる際に、幕屋の供えのパンを食べたことを取り上げられたのです。「このパンはアロンとその子らのものであり、彼らはそれを聖域で食べねばならない。それは神聖なものだからである。」(レビ記24:9)幕屋の供えのパンは、神様と民の契約を象徴する聖なる物であり、誰もが食べられる物ではありませんでした。 聖なる祭司だけが、聖なる場所で食べられる聖別された物だったのです。 しかし、神様に選ばれたダビデは、それを食べて何の罰も受けませんでした。 神様が彼を王として用いられるために守ってくださったからです。 つまり、神にとって、当時のダビデは供えのパンよりも大切な存在だったということでしょう。 もちろん、律法は大事なものです。ダビデと供えのパンの出来事は特別なケースです。ダビデのように絶体絶命の状況でない限り、律法は必ず守るべきです。それでは、弟子たちを咎めるファリサイ派の人々に反論なさったイエスは、律法を無視されたわけでしょうか? 違います。イエスは律法と安息日の存在理由を誰よりも、よく知っておられました。それは、人を人間らしく生きさせるためでした。「イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二も、これと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。(マタイ22:37-40)主はご自分が神の子で、ダビデのような偉い人だから安息日なんて破っても良いという趣旨でダビデを取り上げられたわけではありません。 安息日も律法も大事ですが、そのすべてが人のためのものだから、たとえ安息日だと言っても、人の苦しみと悲しみを顧み、助けなければならないということを教えくださるためでした。御父は、イエスを通して、主を信じるすべての人をご自分の子とされます。当時のユダヤ人の社会、法則、慣習のように、人を歯車のように軽んじるのではなく、一人一人を神の子として愛し、重んじておられるのです。 しかし、ユダヤ社会は旧態依然として、人の生命よりも社会、法則、慣習をより大事にしました。そしてそれは神の御心とは相反するものでした。 だからイエスはこれを問題視されたのです。 締め括り 私たちは先週の大信仰問答を通して、人の在り方について学びました。それは神を知り、崇め、一緒に生きることでした。ところで、イエスは神様との関係に劣らないほど、隣人との関係をも大事にされました。すなわち、イエスは律法を通して、神への愛はもちろん、隣人への愛までも学ぶことをお望みになったわけです。今日の本文の、ファリサイ派の人々は、そんな主の御心が分からなかったのです。 彼らはただ、知識と宗教儀式だけを大切にし、自分たちと違う隣人を軽んじ、それを主の御心だと理解しました。そのようなファリサイ派の人々に向かって、イエスは厳重に宣言されました。「安息日は、人のために定められた。人が安息日のためにあるのではない。だから、人の子は安息日の主でもある。」(27-28)イエスはご自分のことを人の子と言われました。イエスが自らを人の子と呼ばれたのは、神であるご自分が人々の間に共におられることを強調する意味だったと思います。それほど、神は人を愛しておられるのです。新約の時代に安息日というのは、主日だけではありません。主イエスと共に生きるすべての日が安息日であり、主日なのです。したがって、私たちは日曜日の宗教儀式に閉じ籠って、他人を罪に定めず、どうすれば彼らをもっと愛し、共に生きていけるのかと悩みつつ生きるべきでしょう。安息日の主であるイエス様が、私たちにそのような人生を促しておられるからです。