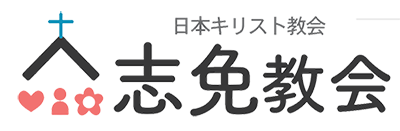神が結び合わせてくださった。
申命記24章1-4節(旧318頁) マルコによる福音書10章1-12節(新80頁) 前置き イエスはマルコによる福音書9章で、神の国においての生き方について教えてくださいました。3人の弟子たちと山の上に登られ、変容した姿を見せられながら、神の御心が人の思いと違うことを示してくださいました。下山の後には弟子たちが追い出せなかった悪霊を追い出され、神の国は口先ではなく信仰の実践によって成り立つということを教えてくださいました。また、自分を低くして他人に仕える者こそ、神の国では本当に偉い者であることを教えてくださいました。最後に他人を排除せず、お互いに理解しあい、仕えあって生きることが神の国の法則であることをも教えてくださいました。神の国を生きるということは、この世の法則とは正反対に行うということを、主イエスは教えてくださったのです。そしてイエスは今日の本文で、この世のやり方とは反対に行く、神の国の法則を結婚という主題を通じて、もう一度教えてくださいました。 1。ファリサイ派の人々が離婚について質問した理由。 今日の本文の冒頭には、イエスを目の敵のように思っていたファリサイ派の人々が、再びイエスを訪ね、主を困らせようと試みる姿が描かれています。「ファリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは、律法に適っているでしょうかと尋ねた。イエスを試そうとしたのである。」(マルコ10:2) 当時、結婚と離婚の問題はイスラエル社会において、非常に敏感なことでした。昨年、マルコによる福音書6章の説教でお話ししましたように「ヘロデ・アンティパスとヘロディア」の不正な結婚を戒めた結果、斬首刑で殺された洗礼者ヨハネに関する問題が、世間で話題になっていたからです。ヘロデ・アンティパスは、当時ガリラヤ地域の支配者で、彼はヤコブの兄エサウの子孫でした。そのため、彼はユダヤ系の血を引いた女、つまり兄弟の妻であり、自分の姪であるヘロディアと無理やりに結婚しました。その過程で二人は元の配偶者との離婚を押し切りました。そういうわけで、彼の離婚と結婚について一言でも発言すると、洗礼者ヨハネのように殺される可能性がありました。だから、皆が言動に非常に注意していたはずです。ファリサイ派の人々は、その点を用いて、イエスの見解を悪用しようとしたのかもしれません。今日のファリサイ派の人々の質問は、単なる宗教的な質問ではなかったのです。 ところで、主はファリサイ派の人々が尊敬している、ある人の名前を取り上げられ、彼らの計略に陥れられずに主の見解を示してくださいました。その尊敬する人とは、律法の重要な人物である「モーセ」でした。「イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたかと問い返された。」(マルコ10:3) このモーセという名前が出てくるだけで、ファリサイ派の人々はイエスを告発することが出来なくなってしまいました。モーセという名前が出た以上、これは政治の問題ではなく、ユダヤ教の宗教的な問題になるからです。「モーセは、離縁状を書いて離縁することを許しました。」(マルコ10:4) 主がモーセの命令について問いかけられた時、彼らは申命記24章1-4節の言葉を思い起こしたでしょう。今日の旧約の本文、申命記24章1節をお読みします。「人が妻をめとり、その夫となってから、妻に何か恥ずべきことを見いだし、気に入らなくなったときは、離縁状を書いて彼女の手に渡し、家を去らせる。」ここで「恥」とは何でしょうか?ヘブライ語の直訳としては「裸、脱いだ下半身」という意味で、象徴的には「汚れ、恥」を意味します。(創世記9:21裸のノアに使われた表現)つまり、妻にこのような「汚れ、恥」がある場合、律法では「離縁状を書いて、妻を捨てることができる」と記されていたのです。 2。結婚を軽んじる世。 「イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。」(マルコ10:5) しかし、主はこの旧約の言葉の本当の意味について改めて語られました。それは「恥ずべきことを理由に、勝手に妻を捨てても良いという意味ではない。むしろ男たちの頑固さにより、女たちが無分別に捨てられないように、また、女性が新しく嫁げるように、神が特別に配慮してくださったのだ。」という意味なのです。なぜなら、ユダヤ人が考えた「恥ずべきこと」にはとんでもないことが多かったからです。保守的な解釈で、この「恥」という言葉は「妻の性的な堕落」を意味する表現でしょう。しかし、その場合、ユダヤでは石に打たれて死ぬに決まっていました。家から追い出されるくらいの恥は、性的な堕落以外のことだったということです。「ヒレル派」というラビの学派では、この「恥」について、こう解釈したと言われます。「妻との関係で満足がないこと」「妻の料理がおいしくないこと」「妻が隣の妻よりきれいでないこと」つまり、恥ずべきことというのが、夫の気に入らないすべてのことだったという意味です。このように、当時イスラエル社会では、あまりにも簡単に妻が離縁されることが多かったようです。そして追い出された妻たちは、日常生活が不可能になり、結局は本当に堕落して売春につながったりあるいは乞食となったりしたのです。しかし、離縁状がある場合は、また別の人と結婚ができたようです。 それだけでなく、特別な場合は、妻が夫を離れることもあったようです。この場合は権力と財産のある富裕層の女性たちにあったと言われます。ローマの詩人であるデキムス・ユニウス・ユウェナリスという人のある詩には、このような語句があると言われます。「前々に合意したでしょう。あなたはあなたの好きなことを、私は私の好きなことをしても良いと。」ここで、好きなこととは自由な性生活のことです。このように、ローマの裕福な女性たちの間では、自由な婚外の性関係、夫の浮気に合わせて自分も浮気をすることが少なくなかったと言われます。おそらく、ヘロデ・アンティパスと再婚するために元夫と離婚したヘロディアも、このようなローマの文化の影響を受けたのかもしれません。いずれにせよ、ローマ時代にも現代人の考えを超える奇想天外なことがあったようです。男が妻を追い出そうが、裕福な女が不倫をしようが、このような姿は主イエスにおいて、神の創造の摂理と合わないものでした。「しかし、天地創造の初めから、神は人を男と女とにお造りになった。それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから二人はもはや別々ではなく、一体である。従って、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」(マルコ10:6-9) 神は離婚を許されなかったのですが、世の中は結婚と離婚をあまりにも軽んじていたのです。 3。離婚が問題ではなく、離婚をもたらす人の罪が問題だ。 人生において、結婚の重要性は、言うまでもないことです。しかし、生きながらやむを得ず、離婚しなければならない場合もあります。結婚10年目に、自分が同性愛者だと打ち明けた夫に離婚された人、妻の不倫によって離婚された人、配偶者の過度なかけ事や株式投資、事業拡張による金銭的な問題のため離婚した人、配偶者の暴力によって離婚した人など、実際に残念な事情を持った人が少なくありません。このように配偶者の過ちによって離婚される場合まで、罪に定めることは現実的に無理だと思います。しかし、家庭をまともに守らない者、浮気で配偶者を捨てる者、配偶者に暴力を振るう者、結婚を軽んじる者、自身の欲望を理由に家庭を壊し、離婚にまで至らせる者は、明らかに罪を犯した者で、神に判断されるでしょう。結婚は大事なものです。神はこの世での人間の歴史をアダムとエヴァという男と女の結婚から始められました。神は夫婦を一心同体として召されました。だから、主はこう言われたわけです。「神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。」 厳密に言えば、今日の主題は離縁についての話ではありません。離婚をもたらす人の罪に対する警告の言葉なのです。わたしたちの教会の場合、50年近くの結婚生活を続けてきた方々がおられます。今までのように、これからも配偶者を愛し、幸せに過ごしてください。やむなく独身でおられる方々も、今後の神の計画がどうなるか分からないので、まず今の周りの人々を大事にして過ごしていきましょう。いつも配偶者の立場から考えて生きましょう。配偶者は神がくださった最も近い隣人です。「あなたがたに対して、神が抱いておられる熱い思いをわたしも抱いています。なぜなら、わたしはあなたがたを純潔な処女として一人の夫と婚約させた、つまりキリストに献げたからです。」(Ⅱコリント11:2) パウロはコリント教会への自身の伝道について、純潔な花嫁を花婿であるキリストに婚約させたことと表現しました。つまり教会は妻であり、キリストは夫であるということです。主イエスはご自分の花嫁である教会のために命を捧げられました。また、歴史上の教会は時々堕落したとしても、必ず夫であるキリストに立ち戻りました。このような主と教会の関係に照らして、夫婦は最後まで互いを見捨ててはならず、愛によって生きるべきです。それがまさに夫婦に向けた神の御心なのです。 教師の働きを始めてから10年が経ちました。この10年間、未信者の主人と結婚した女性信徒さんたちと数多く会ってきました。志免教会にもご主人が教会に通っていない方がおられます。しかし、クリスチャン・ホームでないからといって、あまり失望しないでください。実はその結婚も神が結び合わせてくださった関係だからです。その中で、配偶者に仕え、信仰を守って生きる皆さんの姿を、神はきっと喜ばれるでしょう。自分に許された結婚を大事にして、配偶者を愛することが主の御心であることを忘れないようにしましょう。今日の主題は簡単明瞭です。主がお許しになった結婚を自分の使命と考え、大事にして生きる時、主は褒めてくださるでしょう。そのような生活の中で教会をご自分の花嫁のように守ってくださるイエス•キリストの愛を見つけたいと思います。そして、そのような人生が、この地上において神の国を生きる聖徒の人生の一部分であると信じます。今週も神様の恩恵が志免教会の歩みと共にあることを祈ります。