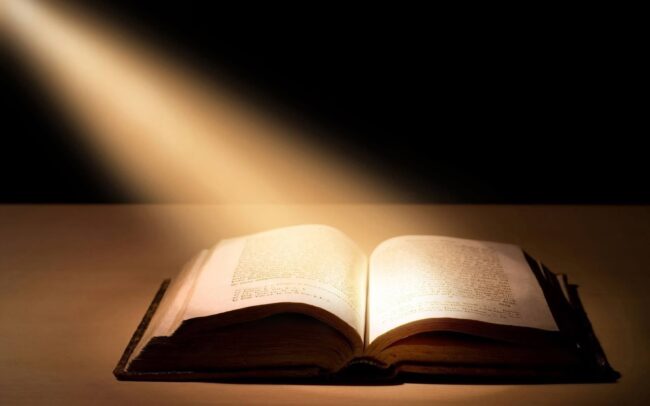上にあるものを求めなさい。
コロサイの信徒への手紙3章1~11節(新371頁) 前置き 今日は、2025年の志免教会の歩みを決める定期総会の日です。総会を始める前に、まず私たちの教会の頭であるキリストの御心を憶え、分かち合いたいと思います。私たちはキリストの体なる共同体として、この世に生きていますが、この世の価値観に属する者ではなく、キリストの価値観に属する者なのです。この地上に生きているが、常に神の右に座しておられるキリストの御心を憶え、その方のご意志に従順に聞き従いつつ生きるべき者であります。だからこそ、私たちはいつも上のものを求めつつ生きなければなりません。今年の我が教会の歩みを決める大事な時間、この地上のものではなく、上におられる主なる神の御心とは何か深く考えて、心を新たにする時間であることを祈り願います。 1. キリストと共に 「さて、あなたがたは、キリストと共に復活させられたのですから、上にあるものを求めなさい。そこでは、キリストが神の右の座に着いておられます。」(コロサイ3:1) イエス·キリストと教会の関係は、ただの主人と召使いのような関係ではありません。その関係は、何よりも深い夫婦関係に近いです。日本語で「主」と訳されたギリシャ語は「王、主人、身分の高い者」に使う言葉でもありましたが「夫」を意味する言葉でもありました。(日本人ならすぐ分かると思います。ご主人という言葉をよく使っているからです。)そのためか、聖書のあちこちにイエス·キリストを「花婿」として、教会をその方の「花嫁」として描いたりします。夫と妻は、金銭や利益によって結ばれる関係ではありません。互いに愛しあい、信頼しあい、体と心が一つになる世界で最も深い関係なのです。イエス·キリストは主の教会をご自分の花嫁にするために十字架で命をかけてまで教会のために贖ってくださいました。したがって、キリストと教会は絶対に分かれることのできない神が一つに結ばせてくださった関係です。今日の本文の1節には、あなたがた(教会)はキリストと共に復活させられたから、上にあるものを求めるべきという趣旨のことばが出てきます。夫を先に亡くした妻のことを「未亡人」と言います。つまり「まだ死んでない人」という意味です。「夫無しには妻も無い」という前近代的な言葉なので望ましい表現ではありませんが、それだけに夫は妻にとって重要な存在であるということです。だから、復活された花婿であるキリストは教会にとって命そのものであり、教会を存続させる一番大事な存在であります。 「あなたがたは死んだのであって、あなたがたの命は、キリストと共に神の内に隠されているのです。あなたがたの命であるキリストが現れるとき、あなたがたも、キリストと共に栄光に包まれて現れるでしょう。」(コロサイ3:3-4)ところで、今日の本文は、教会が「命であるキリストが現れるとき、キリストと共に栄光に包まれて現れる存在」と語っているのです。つまり、以前、イエス·キリストではなく、この世の支配の下にあった私たちは、必ず滅ぼされるべき世の妻のような存在でした。しかし、キリストが私たちを選び救ってくださり、私たちに命を与え、キリストの花嫁にしてくださいましたので、私たち教会はキリストによって命をいただいた存在、キリストと共に生きる栄光の存在として生まれ変わるようになったのです。これが私たち教会のアイデンティティ-を証明する最も強力な根拠になります。したがって、今日の本文は、私たちがキリストに属する存在、この世とは異なる価値観で生きる存在だと述べているのです。 本文はそのような私たちのとるべき生き方について「上のものを求めなさい」と語ります。ここで「上」というのは、私たちがいる土地(この世)ではなく、天(主)の価値観だと言えます。聖書において、「天」は主なる神のご統治を意味する場合が多いです。そして、新約聖書においての神の統治はイエス·キリストの十字架での贖いの出来事によって、キリストの統治に譲られました。 2. 上にあるものを求める つまり「上にあるものを求める」ということの意味は、この地上に属した存在として生まれ、地の支配下にあった私たちが、キリストによってキリストに属した存在に生まれ変わったから、私たちの本当の支配者であるキリストの御心に聞き従い、主の民らしく生きるべきということです。「だから、地上的なもの、すなわち、みだらな行い、不潔な行い、情欲、悪い欲望、および貪欲を捨て去りなさい。貪欲は偶像礼拝にほかならない。これらのことのゆえに、神の怒りは不従順な者たちに下ります。あなたがたも、以前このようなことの中にいたときには、それに従って歩んでいました。今は、そのすべてを、すなわち、怒り、憤り、悪意、そしり、口から出る恥ずべき言葉を捨てなさい。」(コロサイ3:5-8) そして、聖書はこの地に属した者の生き方について上記のように解き明かし、そのような生き方を捨て去るのを命じています。そのような生き方には神の怒りが下るからです。キリスト者として生きるということは、私たちの生まれつきの性格、性質、罪の本性をはじめ、育ちながら身についた貪欲、悪い行いなどと一生戦って生きなければならないということを意味します。キリストを知らなかった時の私たちは、自分の気の向くままに生きてきたが、キリストの花嫁になった今は、主の御心とは何であるかをわきまえ、自分にある望ましくない生き方を節制し、主の御心にふさわしい生き方を追い求めて生きなければならないのです。そこに信仰生活の難しさがあります。自分の本能との真っ向勝負だからです。 「造り主の姿に倣う新しい人を身に着け、日々新たにされて、真の知識に達するのです。そこには、もはや、ギリシア人とユダヤ人、割礼を受けた者と受けていない者、未開人、スキタイ人、奴隷、自由な身分の者の区別はありません。キリストがすべてであり、すべてのもののうちにおられるのです。」(コロサイ3:10-11) しかし、キリストによって新たになった私たちは、主を知らなかった時代の私たちとは明らかに異なる新しい生き方で生きなければなりません。キリストの花嫁となった私たち、キリストに属して新たに生まれ変わった私たちは、天地創造の時に主なる神がご計画なさった真の人間の姿、すなわち、造り主なる神の姿に倣い、回復した望ましい人間として以前とは違う人生を生きなければならない課題を持っているからです。主イエスは人種と文化と国籍を超えて、主に属し、主の御心に従って生きる者たちに新しい人生を与えてくださいました。主はユダヤ人、異邦人、未開人、残酷すぎだったと言われるスキタイ人、奴隷と自由人を問わず、主によって新たになり、主の民となった者たちに差別なく恵みと力を与えてくださいました。依然として私たちには罪の本性が残っており、完全に新しくて正しい人生を生きることは難しいかもしれませんが、それでも、私たちの中に一緒におられ、導いてくださるキリストは、差別なく愛によって私たちを正しい道に導いてくださいます。その主イエスのお導きに信頼し、主の御心を追い求めて生きることこそが「上にあるものを求める」人生ではないでしょうか。 締め括り 2025年にも、私たちは多くのことを経験するでしょう。嬉しいことも、悲しいことも、楽しいことも、辛いこともあるでしょう。しかし、私たちが、どの方の民なのか常に憶え、どのように生きるべきかをよくわきまえながら、主の御心とお導きを求め、上にあるものを求めて生きる私たちでありますように祈ります。私たちの中にある罪の本性を節制し、主の御言葉によって私たちに聞こえ響いてくる正しい生き方を貫き、主イエス·キリストに属した者にふさわしく生きていきたいと思います。主なる神が今年一年も、志免教会の兄弟姉妹みんなに豊かな恵みと愛とを注いでくださいますよう祈ります。そして、今日の総会にもその恵みと愛が与えられますよう祈ります。