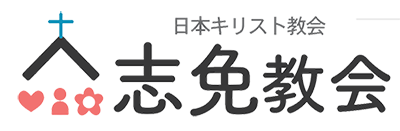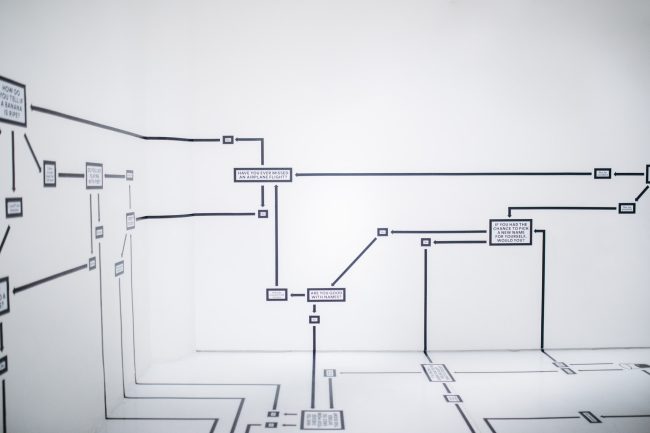祈り
歴代誌下7章14節(旧679頁) マタイによる福音書6章5-8節(新9頁) 前置き 祈りとは何でしょうか。私たちは、祈りによって礼拝を始め、祈りによって礼拝を終わります。また、祈りたけのために水曜祈祷会を守り、常に個人の祈りをし、中会、大会の時も祈りによって始まります。そして、聖書も祈りについて、非常に大事に扱い、主イエスも生前に祈りの歩みを歩かれました。このように祈りはとても大事なキリスト者の信仰の行為なのです。今日は、聖書の御言葉を通して、この祈りというものについて一緒に考えてみたいと思います。 1.旧約時代の祈りの場-神殿 「あなたは天からその祈りと願いに耳を傾け、彼らを助けてください。(歴代誌下6:35)」歴代誌下6章にはソロモンの祈りが記してあります。エルサレムの神殿が完成された日、ソロモンは神殿で祈りました。彼は神がご自分の民を哀れみ助け、最後まで導いてくださることを願いました。ソロモンはイスラエルの神だけがイスラエルの主であり、助けてくださる全能者であると祈りました。すると、神はその夜にソロモンの夢に現れ、今日の旧約本文のように言われました。 『もし、私の名をもって呼ばれている私の民が、跪いて祈り、私の顔を求め、悪の道を捨てて立ち帰るなら、私は天から耳を傾け、罪を赦し、彼らの大地をいやす。』(歴代誌下7:14)神はソロモンが捧げた神殿をご自分の民の祈りを聞かれる場所にしてくださいました。「今後この所で捧げられる祈りに、私の目を向け、耳を傾ける。今後、私はこの神殿を選んで聖別し、そこに私の名をいつまでも留める。私は絶えずこれに目を向け、心を寄せる。」(歴代誌下7:15-16)イスラエルの神殿は特別な場所でした。神殿に当たる概念は出エジプト記の時代にもありました。その時は幕屋と呼ばれる仮小屋でしたが、それは主がくださった十戒の石板が入った契約の箱が置かれる場所でした。契約の箱は神の足台とも呼ばれましたが、それは神がこの地上に直接関わっておられるという意味でした。幕屋は人間の罪のゆえに神との関係が崩れたこの世に、神が積極的に関わられ、特に神に選ばれた民と一緒におられることを示す、神のご臨在の象徴でした。ところで、ソロモンはその幕屋をいっそう大きくアップグレードして、神が「主の名をもって呼ばれている神の民」と共におられることを望んだのです。しかし、それは単にイスラエルの民だけに限られることではありませんでした。他民族が神殿に来て主を認め、謙遜に祈る時、彼らも受け入れてくださる、異邦への主の救いの象徴としてもしようとしたのです。 神殿で祈る時、神は祈る者を助け、癒してくださると約束されました。しかし、残念なことに現代のエルサレムに神殿はありません。西暦70年にローマ軍によって破壊されました。それでは、神殿の新約時代に、私たちはどうすれば良いでしょうか?単刀直入に 旧約聖書の神殿は、新約のイエス・キリストを意味する重要な象徴であります。これは新約聖書からも知ることが出来ます。『イエスは答えて言われた。この神殿を壊してみよ。三日で建て直してみせる。イエスの言われる神殿とは、御自分の体のことだったのである。』(ヨハネ2:19-21)旧約の神殿は、神がご自分の民と会ってくださる場所でした。神の民も、神を認める異邦人も、この神殿で神の御前で祈ることが許されたのです。そして、新約時代はキリストにあって神に会い、祈ることが出来ます。もちろん、イエス・キリストは建物ではありません。しかし、この旧約の神殿のようにイエスを通じて、私たちの祈りが神に捧げられるのです。神殿は祈りの家でした。そして、 現代においては、神が神殿として認めてくださったイエス・キリストの、御名によって祈ることが出来るようになりました。私たちが祈りを終える時、いつも「主イエス・キリストの御名によって祈ります。」と唱えることには、このような意味があるからです。昔の神の民は神殿で祈りました。つまり、私たちは新約の真の神殿であるイエス・キリストにあって祈るべきということです。別の名を通じては、私たちの祈りが父なる神に届くことが出来ません。神が「私の名をもって呼ばれている私の民」と言われた部分を記憶したいと思います。私たちが神にいただいたその名、イエス・キリストの名によって祈るとき、私たちの祈りは、あの旧約の神殿での神の民の祈りのように神にささげられるのです。 2.祈りは調律。 今日の新約本文は、イエスが弟子たちに「主の祈り」を教えてくださる前の物語です。「あなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れた所におられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば、隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。」(マタイ6:6)イエスの時代には、ラビや宗教指導者が広場や神殿の庭で他者に目立つように大声で祈る場合があったと言われます。そのような祈りを通して、「私はこんなに素晴らしい祈りをする。律法についてよく知らない君たちより、私の方がはるかに正しい人である。私は君たちとは違う。」ということを見せて、自分の義を自慢するためでした。しかし、イエスは、むしろ小部屋に入ってひそかに祈ることを命じられました。祈りは他者に見せるために、あるいは自分自身の欲望を満たすためのものではありません。 祈りは調律です。演奏者は、演奏の前に基準音に合わせて調律をします。オーケストラの公演に行くと、公演を始める前に、オーボエ奏者が『ラ音』を出すそうです。この音に合わせて全ての楽器は調律します。これが基準音です。祈りは、神の基準音、すなわち、神の御心に信徒が自分の基準を合わせる行為です。祈りを通して神の御心を基準音とし、それに従って生きていくということです。ですので、私たちは、調律の祈りをするべきです。自分自身の欲望と罪を神の御前で抑え切って、神の御心に沿って行くことを求める行為です。だから、自分の願いを叶えようとする意図だけでは、完全な祈りを捧げることは出来ません。もちろん、私たちは、経済、子供、健康、人間関係のために祈る必要があると思います。しかし、その祈りは私たちの弱さを告白する祈りとなる必要があります。自分が金持ちになり、権力者になって、欲を満たす祈りではなく、自分の祈りを通して、経済、子供、健康、人間関係への自分の弱さを告白するということです。叶えてくださるにせよ、拒まれるにせよ、神に自分の事情を打ち明けることが大事だということです。そして、神が与えられるお答えに応じて、願いが叶っても感謝し、叶わなくても感謝することが重要です。そして、そのような祈りの中で最も重要なことは、神の御心とは何かを悟り、それに自分の心を共に重ねていくことです。イエスはこのような調律としての祈りを強調されたのです。 3.主イエスの御名によって祈る。 神はイエス・キリストを現代の神殿にしてくださいました。私たちが主イエスの名によって祈る時、その祈りを聞いてくださいます。この会堂は神殿ではありません。ただ建物に過ぎないのです。この会堂が無くても、私たちは公園で礼拝することが出来ます。志免教会の始まりは、この会堂ではなく、家庭礼拝からでした。誰かの家での集いも主イエスによって教会になるということでしょう。主の御名によって集まる所が教会そのものだからです。しかし、神がくださった真の神殿であるイエスの御名がなければ、私たちの祈りは、御父に届くことが出来ません。また祈りは神の御心に自分の心を合わせていく行動です。主イエスが父なる神の御心に合わせて、ご自分の命を捧げられたように、祈りは自分のことを神の御心に合わせる行為なのです。神が望んでおられることを自分の基準にし、それに合わせることです。その基準に合わせて、神は私たちの願いを叶えられるか拒まれるのです。しかし、その神の御心に従って叶っても感謝、叶わなくても感謝する成熟した信仰を持っている私たちになりましょう。 イエス・キリストの名によって祈りましょう。そして、その祈りを自分の欲望と必要だけのためにではなく、神の御心とは何か?自分がどのように神の御心に気づいて行くべきだろうかのために祈りましょう。『あなたがたの父は、願う前から、あなたがたに必要なものをご存じなのだ。』(マタイ6:8)神は、すでに私たちの必要を知っておられる方です。神の御心に合わせて、私たちに必要な祈りを聞かれ、その願いを叶えてくださると信じます。しかし、時には、自分の思いが神の御心に合わない場合、拒まれるかも知れません。それでも絶望せず、神の正しさを信じて従って行きましょう。神は、主の民を愛しておられます。神は、主の民が最も良い道に行くことを望んでおられます。私たちに良いものを与えてくださる神を信じて、何のために祈って行くべきかについて、毎日、主に伺って行きましょう。その時、神は私たちに最も必要なものを喜んで答えてくださるのでしょう。 締め括り 今後の祈りを通して、私たちの人生を通して、神が許されたイエス・キリストの御名によって、神に自分を捧げて、神の御心に自分を合わせて、へりくだって真実な祈りを捧げる志免教会になっていきましょう。常に神の御心に聞き従い、その御心を私たちの基準として生きていく志免教会になることを祈り願います。